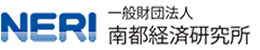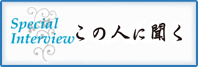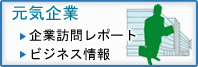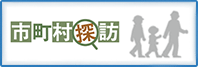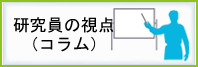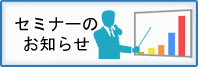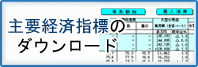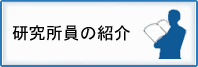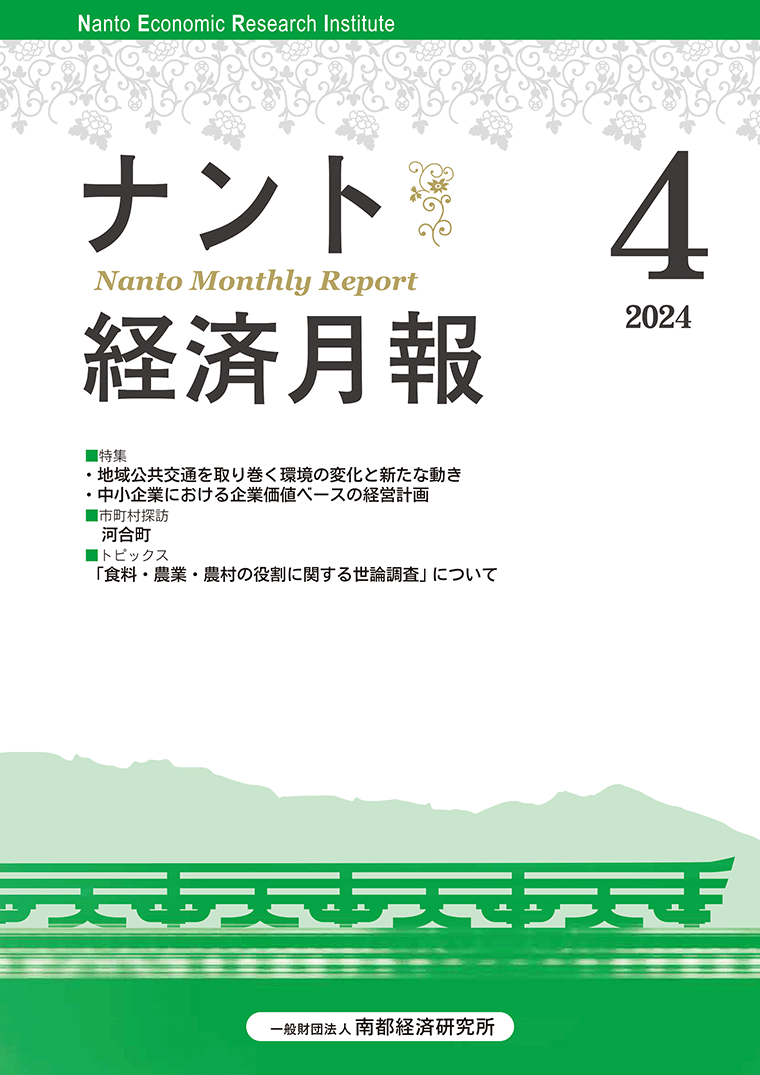タクシーは、鉄道やバスとともにわが国の地域公共交通を形成しており、長年にわたる需給調整規制注1)により新規参入が制限されてきた。2002年に同規制は完全撤廃されたが、輸送人員の減少に歯止めがかからない中で車両数が増加したことからドライバーは低賃金や過重労働に直面し、サービスの質の低下や重大事故の増加を招くこととなった。そこで2009年には特定の地域において新規参入要件を厳格化するなど、地域公共交通としての機能を維持するための規制が再び強化された
このようにタクシーは、地域社会において重要な役割を担っておりその存在意義は大きいが、労働条件の面から若年層を中心に就職先としての人気は低く、同じ業界のバス、トラックと比べてもドライバーの平均年齢は高くなっている。そこにコロナ禍が追い打ちをかけ、収入の減少や感染への恐怖による離職者が相次いだ。現在は観光客の増加や宴会の復活などからタクシー利用者は回復しているが、ドライバーの数はコロナ前の水準に戻らず、都市部を中心にタクシー不足が深刻化している。そこで注目されるのが、一般ドライバーが自家用車を使って有償で乗客を送迎する「ライドシェア」である。
2024年4月、「日本版ライドシェア」が解禁され、まず東京23区や京都市域などの主要都市部で、タクシーが不足する時期・時間帯に限り、ライドシェアが開始された。日本版ライドシェアの特徴は、タクシー事業者の管理の下で、地域の自家用車・ドライバーにより運送サービスが提供されることで、利用者の安全や地域公共交通の存続に懸念を示すタクシー業界に配慮した形となっている。
ポストコロナでのタクシー不足の顕在化もあり、制度創設までの流れはスピード感を以って進められた感があるが、その要因の一つにここまで法改正を伴っていないことがある。具体的には、タクシー不足の状況を、道路運送法第78条第3号「公共の福祉を確保するためやむをえない場合」であると解釈して、国が許可を行っていくことにしたものである。このように日本版ライドシェアは移動困難者の解消を主な目的にしていることから、タクシー業界も一定の理解を示している。
次に利用者の視点からタクシーとライドシェアの問題を考えてみる。国が実施した利用者アンケート注2)では、「タクシーを利用する場合に重視する点」(複数回答)として「安全・安心」(57.8%)が最も多く回答された。その他の回答としては「運賃の安さ」(43.3%)、「拾いやすさ」(28.1%)などがあるが、これらはあくまで安全・安心を前提に回答されたものであろう。利便性や価格面を重視した規制緩和は、利用者目線からも本末転倒であると考えられる。
政府は2024年5月にタクシー事業者以外にも参入を認める「全面解禁」に向けた法整備を行うための論点整理を行ったが、タクシーとの共存共栄を図る上での懸念事項を明記するなど、引き続き業界に一定の配慮を示した内容となっている。大阪・関西万博開催時の移動手段の不足を解消する方策としてもライドシェアは注目されているが、日本版ライドシェアの運用状況を評価・検証し、地域の足としての機能を最優先に持続可能な制度設計を行っていくべきだろう。
注1)過当競争による安全性低下の防止、独占性を付与することで収益性を確保し、輸送サービスの質の確保を目的とした規制。
注2)国土交通省 平成30年度 政策レビュー結果(評価書)「タクシーサービスの改善による利用者利便の向上」より抜粋。