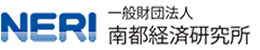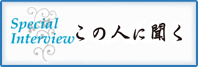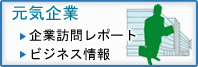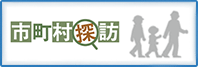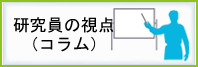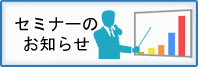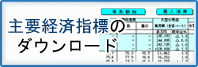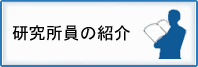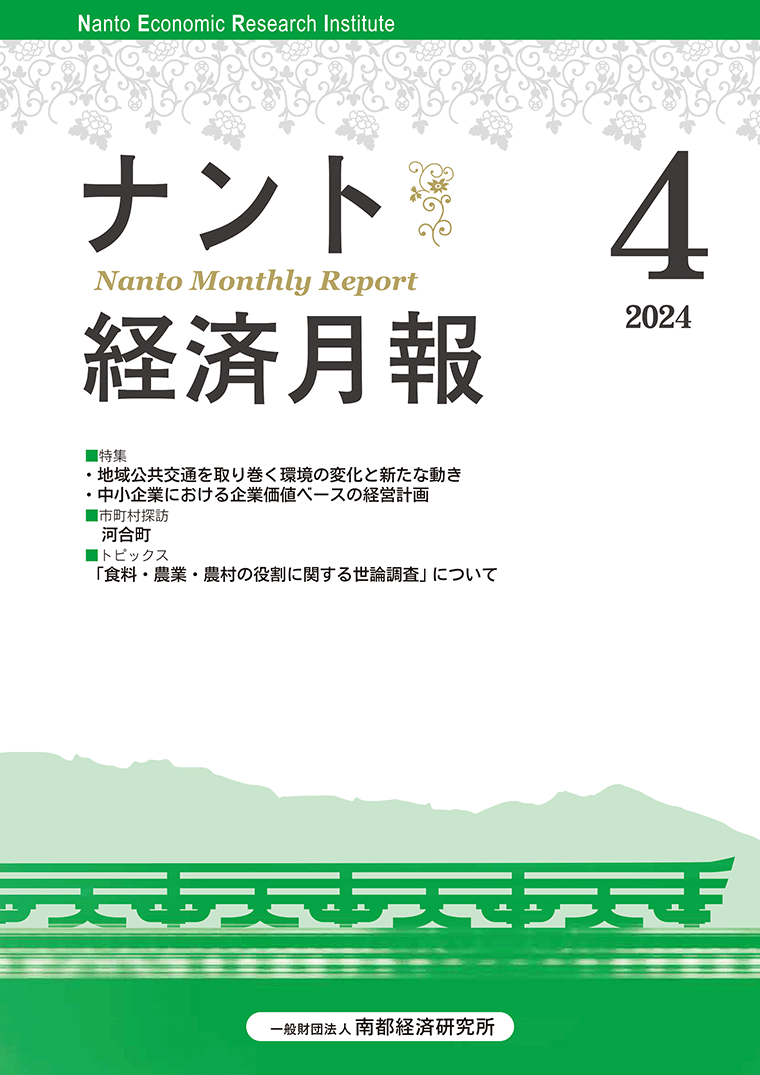■公的年金のしくみ
公的年金(以下、年金)は原則65歳から支給されますが、受給の開始を早める「繰り上げ受給」や、受給の開始を遅らせる「繰り下げ受給」も選択できます。年金の受給開始時期は60歳から75歳まで自由に選択できますが、受給開始を遅らせるほど受け取れる年金額は増えていきます(下図参照)。
繰り上げ受給、繰り下げ受給とも1ヵ月単位で行うことができ、65歳からの年金受給を60歳に繰り上げて早く受給を開始した場合、65歳からの受給額と比べて24%減額(昭和37年4月1日以前生まれの方が繰り上げ受給を選択すると30%減額)された年金額となります。
一方、年金の受給を一月繰り下げると0.7%ずつ増額となり、5年で42%増、最大75歳まで繰り下げると84%増の年金額を受け取れます。
例えば65歳支給の年金額が200万円の人が5年繰り下げると、年金額は42%増の284万円となり、その金額が一生続くことになります。65歳を過ぎても年金以外に一定の収入を見込めるなら、老後対策として受給開始を遅らせるという選択も考えられます。
■繰り下げ受給が得になるとは限らない

老後の資金対策に有効と言われる繰り下げ受給ですが、メリットばかりではありません。早く亡くなると年金の受取総額が少なくなるデメリットがあります。例えば昭和35年生まれの男性(平均余命が84.5歳)が65歳から受給できる年金額を仮に200万円とすると、繰り下げなければ65歳から69歳までの5年間で1,000万円の年金を受け取れますが、70歳まで繰り下げた場合、1,000万円を取り戻すのに約12年かかります。平均余命のほうが長いので繰り下げ受給を選択した方がお得かもしれませんが、年金には税金や社会保険料がかかります。これらの金額は、年金額によって決まるので、繰り下げによって年金額が多くなると、税金や社会保険料の負担も多くなります。そのため年金額が5年の繰り下げで42%増えたとしても、手取りベースでは額面通り増えず、繰り下げた分を取り戻すのに、さらに数年がかかります。
また年金には公的年金等控除があり、65歳以上では年金収入から110万円が控除され所得税・住民税が計算されますが、年金を受給していない繰り下げ期間は、当然この控除を利用できません。さらに繰り下げ受給を選択しても配偶者が受け取れる遺族年金は、増加した年金額ではなく65歳水準で計算された額になるので、そもそも繰り下げのメリットはありません。
逆に繰り上げ受給を選択しても遺族年金は、繰り上げ受給で少なくなった年金額ではなく、65歳水準の額で計算されるので、繰り上げによる減額の影響を受けません。
金利のある世界に戻った今、年金等を運用し増やすことができるなら、繰り上げ受給は、一概に不利な選択ではありません。 (橋本 公秀)